
|
9月28、29日に行われた100km歩行大会に、 今年も社員の家族を含め17名が参加し、12名が完歩しました。 精一杯歩いた新入社員の感想です。 生産技術課 後藤 良太 前半に完歩経験のある方のペースに合わせたことで、 後半は気が楽になって完歩出来ました。 改めて当日の体調、気力、物の準備が大切だと実感しました。 仕事を終えてから応援に来て頂いた皆さん、ありがとうございました。  管理課 中倉 裕也 サポーターの皆様をはじめ、一緒に歩いた方々の声援や助けがあった事で、 最後まで諦めずに歩き切ることが出来ました。 何の練習もしていなかったにもかかわらず、 ゴールに繋がったのも気力が全てだったと感じています。 多くの方々に支えられ、感謝を感じた大会でした。 参加出来てとても良かったです。  ジェット織布課 谷屋 友介 一緒に歩いたメンバーとサポーターのおかげで、 100kmをなんとか完歩することが出来ました。 ありがとうございました。 感謝、感激、感動体験が出来てよかったです。  サイジング2課 中澤 一也 参加するまではこんなに大変なものだと思っていませんでした。 自分は第1チェックポイントまでしか歩く事が出来なかったので、 完歩する事はとてもすごいと思いました。  生産管理部 佐野 知香 想像していたよりとても辛かったです。 しかし、皆で一緒に歩けてとても楽しかったです。 会社の皆と楽しくお喋りしたり、お互いに励まし合ったり、 良い思い出になりました。 準備不足だったので、1人だったらきっともっと早くリタイヤしていたと思います。 一緒に歩いてくださった皆さん、応援して頂いた皆さんには本当に感謝です。 ありがとうございました。リベンジは検討中です…。  ドローイング課 石田 愛 すぐにリタイヤすればいいやという気持ちで参加しました。 会社の人達と楽しく歩いていて、最初のチェックポイントで皆と行きたい!と思い、 行ける所まで行こうと思いました。58km地点で足がどうしようもなく痛かったのでリタイヤしましたが、 58km歩けたことは応援してくれたサポーターの方達や、一緒に歩いてくれた人のおかげだと、 感謝の気持でいっぱいになりました。参加できて良かったと思っています。 ドローイング課 中川 瑞季 最初は軽い気持ちで完歩出来ると思っていました。 でも、最初のチェックポイントでもう足が痛くなりきつかったです。 1人ではなく何人かで歩いていたので、足が痛くなりましたが自分の気持ち以上に歩く事が出来ました。 100km完歩する事は出来ませんでしたが楽しかったです。 サポート隊代表 宮本 智行 サポーターとして各参加者の悲喜こもごもを間近で見させていただきました。 ちょっと昔に「夜のピクニック」という高校生が卒業記念で80kmを歩くという映画で、 その主演の女子高生の、「ただ歩くだけなのに、どうしてこんなにトクベツなんだろう」 という言葉があるのですが、バリューというものは、「歩く・完歩する」という「結果」ではなくて、 そこにおける「ストーリー」であり、「経験」であるということを再確認しました。 リタイヤした人、完歩しきった人、全ての皆さんの2日に感動し共感を覚えました。 どうしても歩きたくないという人は、ぜひサポーターとして最後まで参加してみてください。 感動が味わえます。 |
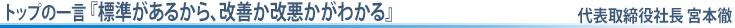
|
「しっかり」「ちゃんと」「きちんと」という指示は標準でない。 人によってとらえ方が変わりますし、ばらつきます。 たとえば「ねじは、トルクレンチでカチッと音がするまで締めろ」という決めごとなら、 音で締めているかどうかわかります。 生産現場に限らず、職場には、こうした「標準」や「決めごと」がない仕事や、 あっても、曖昧な表現(定量的でない)仕事が多いです。 感覚と自分の経験だけで「できる・できない」「早い・遅い」と評価する。 明確な標準があるから、改善か改悪かがわかる。 作業標準書は、作業手順と時間を決めています。 作業標準書通りの仕事ができないなら、それはどこかに問題があるということであり、 作業者を訓練するか、標準作業書を変えるしかない。 変えた結果が良ければ改善であるし、悪くなれば改悪である。 何かを変えるにしてもまずはベースとなる「標準」を決めることが先です。 標準なしに変えることは、結果を曖昧にし評価を感覚的にしてしまいます。 まず標準を決めて守る。 それが、改革や評価のスタートになる。 |

|
先日、行われたTES試験に今年は7名の方が合格しました。 本当におめでとうございます。 中には1発合格という方も…! 合格された皆さんの喜びの声と来年受験する方へアドバイスを頂きました。 営業第2部 宮本 淳二部長 2年目で合格できましたが、1年で合格できなかったことが一番悔しいですね。 基礎問題(3部構成)が分かれば、繊維業界の流れが分かると思います。 この知識が最低限必要になるので身につけてほしいと思います。 勉強は過去問のみをやり、そこに出てくる単語、内容を教科書で確認・整理しました。 帰り通勤中(約45分)をTESの時間にしていました。 営業第1部 平泉 晋さん 2年目で合格出来て良かった、と言うのが正直な感想です。 これも努力の賜だと思っています。 科目によって暗記物もあるので、若い内に受験することはおすすめします。 社会人になって合格するかドキドキ出来る事も少ないと思いますので、 いい機会と思って受験するのもありかなと思います。 テキスタイル開発1課 北口 亜紀奈さん 3年目で合格できました。近さんにはとても丁寧に教えて頂き、 受験料等を会社に助成して頂き、会社の制度に感謝しています。 今後受けられる方へは、近さんの勉強会で集中して学ぶことが一番の合格への近道だと思います。 分からない部分は質問して、頑張って下さい。 品質保証課 中村 法子さん お陰様で何とか2年目で合格することができました。 忘れたり、わからない部分がまだまだ有るので、 面白いと感じた所や解析業務に活かせそうな事例等を中心に、 また少しずつ勉強していきたいです。 社内の勉強会は本当にわかりやすく勉強になったので、 来年から受験する方もぜひ参加をお勧めします。 営業第1部 大井 拓郎さん 正直今年で合格できるとは思っていませんでした。 基本的な内容には回答出来たのですが踏み込んだ内容が回答できていなかった為です。 しかし、基礎的な事をしっかり頭に入れる(1,2,3章) 正確な回答パターン(事例、論文)を必ず練習する。 これができれば合格できます。 テキスタイル開発1課 杉本 和也さん プレッシャーの大きい試験でした。 II.製造,品質、Ⅲ.流通,消費は過去問(IIはテキスト丸暗記が本来有効)、 IV.事例は黄変、汚染、移行昇華、リバースと4つのカテゴリーがメイン、 V.論文は数年分の過去問の解答例を見ると、 そこから頻繁に用いられるワードが複数浮かび上がりました。 800字を要求されている項目に文字数分割し意図している事と望んでいるワードを繋げる方法で解きました。 近さんの勉強会、藤田課長からはテキストを貸して頂き合格することが出来ました。 本当にありがとうございました。 専務付 宮本 智行さん 試験自体は簡単だったので試験終了後、合格したと正直思いました。 繊維という大きな括りで見ると、製織技術はバリューチェーンの一部にすぎないので 視野を広げる試験としては有効だと思います。 アドバイスとして僕はこの10年間ほど努力とか頑張るというネガティブな言葉を使わないようにしていますが、 試験に限らず本来、知らないことを知ることは快楽であると思いますので、 面白おかしくやればいいと思います。 |

|
10月1日(火)に来年4月より入社される大卒、短大卒、 専門学校卒の内定者5名の方々の内定式を実施しました。 社長あいさつ、内定証書授与、自己紹介のあとは先輩社員との昼食会もあり、 楽しく顔合わせをしました。 来年から一緒に働けるのがとても楽しみです!  |

|
創友会の役員が交替となり、前会長の丹後登課長に活動の振り返りと 新会長の中垣課長に抱負をインタビューしました! 生産技術課 丹後登課長 一年間無事に努められたのは皆様の御協力と役員の方達に助けて頂いたお陰と思います。 この場を借りて御礼申し上げます。 最初の行事の忘年会ですが、段取りの難しさを痛感しました。 ベテラン役員さんのアドバイスあったからこそ出来たと思います。 新入社員歓迎会は大がかりなイベントでしたが、臨機応変に対応、協力して頂き乗り切る事が出来ました。 反省点としてボウリング大会は開催予定時期に設備更新が重なり出来なかったことをお詫びいたします。 最後に、行事を通じて役員の連帯感も強まり、終わりとなると寂しい気もしますが、いい思い出が出来ました。 品質保証課 中垣課長 各課より代表を頂き、計18名の新役員で一年間努めさせていただきます。 前役員の方々より良かった点や反省点もお聞きしておりますので、 今年はひと味違った企画を立てていきたいと思いますのでお楽しみに。よろしくお願いいたします。 |
Copyright (C) Marui Group


